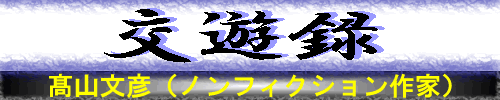
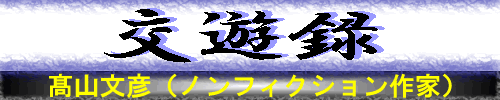
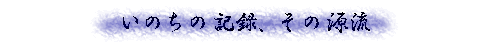
|
髙山文彦氏が本学文学部哲学科に入学したのは一九七七年のことだった。 緑溢れる宮崎県高千穂で育った氏は一年の浪人を経て本学へやってきた。「教員をやっていたおやじの書棚から黴臭い一冊の本を見つけてね。すごく怖いタイトルなんだよ」。セーレン・キルケゴールの『死に至る病』。高校生であった氏には甚だ理解に苦しむ内容であった。「でも、親父が入れたしおりが見つかってね。しおりには、『Hello my dear sweet heart!』と、走り書きがあったんだ。恋人って意味だけど。その恐ろしい題名とのアンビバレントがすごく気になってね」。人間には、生への欲求と同時に死へ向かおうとする本能が存在する。「それで、浪人時代、たくさん本を読んでね。埴谷雄豊、ドストエフスキーとか、古典なら大体読んだんだけど田村隆一の『再開』という詩に『どこで どこでお逢いしましたか! 死と仲のいいお友だち わたしの古いお友だち!』っていうのがあったんだよ。その時思ったんだけど、もしかしたら親父の言う恋人っていうのは、死のことなんじゃないかってね。親父は、もしかしたら、学生時代の一時期、死に恋焦がれたんじゃないかって。そういう、親父の走り書きが僕を哲学とか詩とかそういうものに結び付けようとしたんじゃないかって思うな」。何故、人は生きるのか、死ぬのか、そこに存在するのか。こういった疑問は、後に彼が記す作品へと昇華されていくことになる。 探検部との出会い 「最初オリエンテーションがあって、高校と同じだろ、と思ってたんだよ。授業が自然に組まれるだろって。それで、下宿で連絡が来るのを待ってたんです」。氏は自然と授業登録され、連絡が来るものと思い、ついには初年度の登録を行わなかった。「変だな、と思って、学校に行ったら、語学も体育も始まっててね」。何故だかクラスコンパへは出席した。「神楽坂の今はツインスターがある所に『軽い心』って喫茶店があってね。高価いんだよ。そこに行くと重い心になるって僕らは揶揄してたんだけど、そこで二次会をやったんだ」。授業に出なくとも慌てず騒がずコンパに出席する。当時の学生達の大らかさが偲ばれる。 「で、クラスのコンパなんだけど、経済学部の加納って奴がいて、そいつは経済には女がいないってことで、ナンパしに来てたんだが、そいつと以前映画で見たチベットに行きたいんだ、と話してたんだ。そしたら『俺、探検部ってとこにいるんだ。いつでも行けるぞ』。一年のくせにそんなこと言いやがって。それで、明日からでも入る入るって言って、次の日学生会館七〇六の部室に行ったんだ」。 それから、四年間は校舎へ、ではなく、学生会館に通う日々であったという。「だから、僕は間違いなく、法政大学へ通ったっていうのはないね。授業料は未納で除籍になったんじゃないかな。でも、探検部の部費は払ってたんだ。だから、探検部だけは間違いなく卒業したよ」。 肉体の苦痛の中で「学団連の執行委員もやってて、そこでは、頭ばっか使ってたけど、探検部でよかったのは肉体を使うってことだな」。山を登り、沢を下り、島に渡る。春夏秋冬、手垢のついていないフィールドを探す。歴史的発見をしたこともある伝統と実績あるサークルとして、探検部は現在も活動を続けている。「やっぱり、一年のときは、重い荷物をもたされるんだよ。バテて、バテて、何かを考える余裕なんてないんだよね」。しごきにも似た仕打ちに肉体を追い詰めた。「今でも歩く時ね、歩き方を覚えているんだよね」。氏は精密な取材を元にした、人間描写に優れた著作を数多く世に出している。執筆において、必要なのは繰り返すまでもなく、取材である。足で稼ぐことである。「山を歩く時でも、街を歩く時でも、足が歩き方を覚えているんだよ。平地なら平地の足の置き方、斜面なら斜面なりの足の運び方を。そうすると、余裕が出てくる。観察できるようになってくるんだ。色んなものが見えてくる。そういえば、探検部のOBには、文筆業が多いなあ」。 死を意識するような恐怖に耐えることもあった。厳冬の富士山において行われる滑落訓練。腰に結ばれたカラビナから伸びるザイルを文字通り命綱として、斜面を登っていくわけだが、もちろん滑りおちる場合もある。そのための訓練だった。「それを確保するのも又、大変。肩には、ミミズバレができたりして」。時には、事故が起こることも。そんな中で「覚悟」が培われていった。 生かされている存在一九七七年度探検部夏合宿は福島県、奥只見で行われた。銀山湖から伸びる片貝沢のほとりの草地に、ナタを振るい、ベースキャンプを設営した。氏が参加したC班は、会津駒ケ岳より流れる日本有数の難所と言われる御神楽沢を上った。真夏でありながら、冬に降り積もった雪が残り、固まり、沢の上に張り出していた。もしも地面と間違え、沢の雪を踏み抜いてしまえば、そのまま、激流の中に身を任すより他ない。冷気は冷え冷えと肌を刺し、直径四,五メートルはあろうかという雪柱が目に入った。 「ちょうど、三段ある滝を登りきった時だった。滑って滝の落ち窪んだ所に落ちたんだ」。水に流され、そのまま、断崖へと向かっていく。「あきらめてたんだよな、俺。岸壁に手を当てようともしなかった。プカプカ浮いていた」。迫りくる死を現実のものとして考えることはなかった。「よくここまで、死体になるために登ってきたもんだなあ、とか、三日も登ってきたから、このまま山頂に自分の遺体を上げて、降ろすしかないだろう。仲間に申し訳ないなとか、そんなことばっかり考えていた」。そんな時に目に入ったのは、茶褐色に枯れた苔であった。 「一つ目、二つ目は見送ったんだよ。ところが、三つ目は美しい緑色に輝いていたんだ」。とっさに手を伸ばし、苔に爪を埋め込んでいた。すると、不思議なことに流れは止まり、氏は慌てて岸に上がった。後の探検報告書によれば、素朴にただ、注意不足と仲間への反省を記しているが、「うまく言えないけれど、その時、初めて、自分は緑によって生かされているんだと思ったんだ。まだ、覚えているんだ、あの柔らかい感触」と語る。宮崎の山里で育った氏にとって、緑は身近なものだった。しかし、複雑な思いもある。ある文に氏は、大学の頃を振り返ってこう書いている。『緑まみれの故郷を爆破したいと、渓谷のひとつひとつにダイナマイトを仕掛けて廻る自分の姿を想像した』。 しかし、赤子の時より氏をゆったりと見守ってきたのは、緑輝く木々であり、山であり、氏が出会ってきた人々のはずだ。自己の肯定、そんな言葉が連想される。 水先案内人達とのめぐりあい授業料未納で学校を辞めたのは、一九八一年。七ヶ月ばかり製版会社に勤めた。「その頃電話がなくて、ある人から電報が届いたんだよね」。髙山氏が自主法政祭で催した講演会で招聘し、その後も親交のあった詩人、清水昶氏の知人で、同じく詩人の藤田晴央氏からの電報だった。「彼は、日本テレビで嘱託として働いていてね。日本テレビの運動部でADを募集しているからやってみないかってことだったんだ」。日本テレビに二年勤めた髙山氏は、その後フリーライターに。「そのときは、作家になろうだなんて思っていなかった。とにかく、たくさん原稿を書きたかったけれど、何を書いていいかわからなかった」。 そんな折に、再び藤田氏の知人から編集プロダクションへ紹介があった。「ただ、そこの社長が、うちより勉強になるところがあるからそっちに行けって。人身売買だって怒ったんだけど、明日会うことに決めてるからって」。次の日、新宿で会ったのは、ドキュメンタリーノベルの作家、大下英治氏だった。少ない時は二人、多い時は十人のスタッフの中の一人として、八年間勤め上げた。髙山氏が一艇の船の船長であり、人生という沢を下っているとすれば、水先案内人達は入れ替わり立ち替わり現れ、彼を導いていく。 「何故だか、自分で作家になったという気がしなくてね。誰かにしてもらったという感じで。八年も勤めていると、そろそろ出ていけって言う雰囲気になってくるんだよ。もういいから、後は一人でやれって。それに自分の名前で書きたいという思いも湧き上がったんだ。自分がミスを犯せば大下さんが責められる。それが居心地悪くて」。 不思議なことに、そんな時にはタイミングよく新たな水先案内人が現れる。しかし、それは最後の水先案内人となる。「編集者から電話があってね。そろそろ一人で書いてみないかって」。雑誌「プレジデント」を皮切りに、氏の名で書き始めた。作家になったのだ。 生の肯定彼もまた、彼の著作の中に登場する人物達のように、命を燃やして生きてきたように思えてならない。『勇猛果敢にして、図抜けた判断力と統率力を持つ、一人の男のもとで、自治会や学生会館を奪われぬよう裏で立ちまわった。父殺しを夢見ては、絞め殺してやりたい自我にあえいでいた』。 氏は『命の現場に下りていくような作品を書きたい』とあるインタビューに語っている。 「緑に生かされる」という悟りに至り、その思いが自己の心中において熟成された時、破壊的欲求は取り払われ、代わりに立ち現れたのは自己と他者に対する肯定。生に対する肯定であっただろう。 「大学時代は何を思い出しても、楽しかったなあ」。うっとりとした表情で遠くを見やった。 取材・文 宮田 清彦 |
COPYRIGHT(C)法政大学新聞学会
このホームページにおける全ての掲載記事・写真の著作権は法政大学新聞学会に帰属します。
無断転載・流用は禁止します。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
